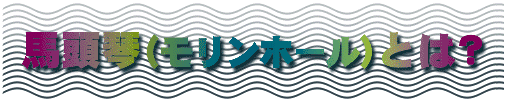
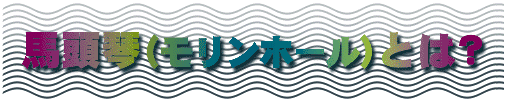
|
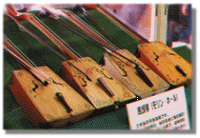 ▲現在の馬頭琴(内モンゴル)  |
■草原のチェロ 馬頭琴(モリン・ホール)■ 馬頭琴(モンゴル語でモリンホール)はモンゴル民族を代表する最も有名な民族楽器です。
弦は2本です。内絃および外絃といいます。棹(さお)の先に馬の頭が彫刻してあることから、中国語では馬頭琴(琴は楽器の意)、モンゴル語ではモリン・ホール(馬の楽器)と呼ばれています。 馬を家族のように愛するモンゴルの人々にとって、馬頭琴は深い愛着のある、特別な楽器なのです。 弓で弦をこすって音を出す擦弦楽器で、元々は馬の尻尾の毛や皮を使って作られていました。 その起源は古く、バイオリンやチェロなどの原点かもしれないと言うロマンチックな説もあるほどです。 音域は、ほぼ2オクターブ半ほど。その音色は太くやわらかく、聴くものの心を揺さぶります。 それぞれの絃は100本以上の細いナイロンテグスか、あるいは70〜80本以上の馬の尾の毛で作られています。 内モンゴル製の馬頭琴はナイロン弦を、そしてモンゴル国の馬頭琴は、主に馬の尾の毛を弦として使用し、時にナイロン弦を使用してています。 ともに絃は束になっていて、内絃・外絃ともに1本1本が平行で、よじれていない事が、美しい音を出すための重要なポイントです。 共鳴箱(ボディーあるいは琴箱)は、今でこそほとんど全てが木製 ですが、ほんの30数年程前まで馬・牛・蛇などの皮を表面に使ったものも多くありました。(左の写真参照ください) 弓は、以前は張力の調整ができないような素朴なものでした。 現在ではバイオリンやチェロの弓とよく似た形状のものが使われることが多くなりました。 (ただし、フロッグと呼ばれる部分の形状が西洋の楽器と異なる) 馬頭琴はオルティンドー(モンゴル独特の歌)などの伴奏に使われる事が多かったのですが、楽器の進歩と共に音楽性・表現力が高まりました。いまでは独奏(あるいは合奏)のための楽器として登場する場面がほとんどとなりました。 千年の歴史を秘めつつ、新しい時代を迎えようとしているいま注目の楽器、それが馬頭琴です。
その音色は、なぜか日本人の心にやさしく沁み込んで来るのです。 【追記】 モンゴル国の馬頭琴(モリン・ホール)と内モンゴルの馬頭琴とでは現在では次のような点で異なっています。 ・形状・寸法 主に琴箱の寸法・形状、音孔の形などが異なる。 ・調弦用糸巻き部分の構造 内モンゴル製は金属製ギヤを使用。 モンゴル国はバイオリン等と同じく、金属部品は使わない。。 ・音域 (調弦) 内モンゴル製が音域が高い。 ・共鳴箱(琴箱)の表面板の材料 内モンゴルは桐など。モンゴル国はスプルースなど。 ・弦の材料 内モンゴルではナイロンテグスを使用。 モンゴル国では基本的に 馬の尻毛を使用する場合が多い。 ただし、モンゴル国の奏者でも、日本で演奏する場合はナイロン弦に 替える例が多いとも聞く。 |